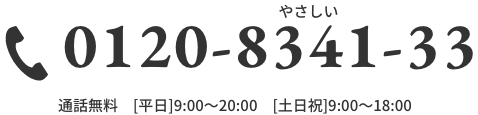定期預金より“定期投資”が常識に?2025年版・ほったらかし投資の正解 2025-10-09 12:36:30

定期預金より“定期投資”が常識に?2025年版・ほったらかし投資の正解
目次
「貯金しても増えない時代」が、いよいよ現実に
かつて、将来のためにお金を「定期預金」で積み立てるのは当たり前の行動でした。
しかし、2025年の今、「銀行に預けてもお金が増えない」どころか、「実質的には減っている」ことに気づく人が増えています。
日本銀行のデータによると、メガバンクの定期預金金利は年0.002%〜0.02%程度。100万円を1年間預けても、増えるのはわずか20円ほどです。
一方で、インフレ率は2024年以降、2〜3%前後で推移しています。つまり、名目上はお金が減っていなくても、物価上昇によって“実質的に目減り”しているのです。
こうした背景から注目されているのが、「定期預金ではなく、定期投資」という考え方。
今や「貯める」から「増やす」へ。投資が特別な人だけのものではなく、誰にとっても“家計の一部”になりつつあります。
定期投資とは?──初心者でも続けやすい「自動積立型の投資」
「定期投資」とは、毎月決まった金額を自動で積み立てて運用する方法のこと。
たとえば、月1万円を投資信託や株式、ETF(上場投資信託)に積み立てるなどです。代表的な制度として「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ)」が知られています。
この方法の大きなメリットは、タイミングを気にせず投資を続けられること。
投資の世界では「安く買って高く売る」が理想ですが、実際には価格変動を読むのは難しいもの。
定期投資では、毎月一定額を買い続けることで「高い時には少なく、安い時には多く」自動で購入されるため、平均購入単価が下がる効果(ドル・コスト平均法)が期待できます。
つまり、時間を味方につける投資です。
“ほったらかし”でも成果が出る理由
定期投資の魅力は、「ほったらかしでも成果が出やすい」点にあります。
投資初心者の多くが挫折する原因は、「いつ買えばいいか分からない」「価格の上下で不安になる」という心理的な壁。
しかし、自動で積み立てを続けることで、そのストレスを大幅に減らせます。
実際に、金融庁が示す過去データでは、20年以上つみたてNISAを続けた人の9割以上がプラスのリターンを得ているという結果もあります。
これは短期の値動きに一喜一憂せず、長期で時間分散した効果が現れている証拠です。
そして何より、定期投資は“行動の習慣化”に優れています。
一度設定すれば、あとは口座から自動で引き落とされるだけ。
「気づいたら資産が育っていた」という“ほったらかし投資”の理想が、テクノロジーによって現実化しているのです。
2025年の「投資環境」はこう変わった
2024年に始まった新NISA制度は、2025年も投資の主役です。
年間投資枠が拡大され、つみたて投資枠は120万円、成長投資枠と合わせて最大360万円まで。
しかも非課税期間が“無期限”となり、これまでのような「20年で終わる」制限がなくなりました。
また、AIを活用したロボアドバイザーや、リスク許容度に応じて自動リバランスしてくれる投資信託も増加。
自分で銘柄を選ばなくても、スマホ一つでプロ級の運用が可能な時代になりました。
さらに、インフレが続く現代では、「現金の価値を守る」ために投資するという発想が広がっています。
もはや「投資はリスク」ではなく、「投資しないことこそリスク」という認識が主流になりつつあるのです。
実際に増えた人たち──“定期投資”のリアルな成功事例
例えば、30代会社員のAさん(年収450万円)は、3年前に「つみたてNISA」で月2万円をスタート。
途中で価格の下落も経験しましたが、売らずに継続した結果、2025年現在の評価額は約90万円→108万円に増加しています。
Aさんは「途中で下がっても“積立中なら安く買える”と考えたら、気持ちがラクになった」と話します。
また、主婦のBさんは家計の余りを「ロボアド」に毎月1万円積み立て。
AIが自動で銘柄を分散してくれるため、知識がなくても運用可能。
3年で運用益+14万円を達成し、「預金よりもお金が働いてくれている実感がある」と語ります。
このように、専門知識がなくても、“習慣としての投資”が結果を出す時代になっているのです。
初心者が始めるなら「3つのルール」を意識
「投資に興味はあるけど怖い」という人も少なくありません。
そんな方が安心して始めるためのポイントを3つ紹介します。
① 余裕資金で始める
生活費や緊急時の資金(生活費3〜6カ月分)は手元に残し、余った分を投資に回すのが基本です。
「投資=全財産を賭ける」ではなく、「使わないお金を働かせる」という考え方を持ちましょう。
② 目標期間は「10年以上」
短期で利益を狙うのではなく、長期で資産を育てる意識を。
複利効果(利益を再投資して増やす力)は、10年以上で本領を発揮します。
焦らず、時間を味方につけるのが鉄則です。
③ 無理のない金額でコツコツ
最初は月5,000円や1万円からでも十分。
投資額よりも「続けること」が成功の鍵です。
自動積立なら、心理的な負担も少なく続けやすいでしょう。
“AI×ほったらかし投資”の新常識
2025年は、AIと投資の融合が進む年でもあります。
たとえば「AIポートフォリオ診断」では、投資家の性格・支出傾向・年齢などから、
最適な投資配分を自動で提案してくれるツールが普及。
過去の市場データをもとに“下落時にどう行動すべきか”をAIが助言してくれるサービスも増えています。
これにより、「投資の知識がないから不安」というハードルが一気に下がりました。
もはや投資は、“専門家だけの世界”ではなく、“AIと一緒に歩む世界”。
これも、ほったらかし投資の追い風となっています。
定期投資の落とし穴──“放置しすぎ”には注意
「ほったらかし投資」とはいえ、完全に放置していいわけではありません。
たとえば以下のようなタイミングでは、年に1〜2回はチェックしましょう。
●生活スタイルが変わった(転職・結婚・出産など)
●投資目的が変化した(教育資金から老後資金へなど)
●リスク許容度が変わった(収入減や支出増など)
また、投資信託の手数料や、運用方針の変更なども見直しポイントです。
「自動化+年1回の見直し」くらいが、理想的な“ほったらかし”の距離感です。
投資で失敗しないための“3つの心構え”
①短期的な損益に一喜一憂しない
②SNSや周囲の情報に流されない
③目的を明確にしておく(何のための投資か)
この3つを守るだけで、感情的な判断を減らし、投資の失敗を防ぐことができます。
特にSNSでは「〇〇が急騰!」「この銘柄が爆上げ!」などの刺激的な情報が溢れていますが、
定期投資においては、“何もしない勇気”こそが最大の武器です。
お金を「貯める」から「育てる」へ
「投資は怖い」「自分には関係ない」と思っていた人ほど、定期投資の効果を実感することが多いです。
なぜなら、投資とは“お金を使うこと”ではなく、“お金に働いてもらうこと”だからです。
定期預金が「守るお金」だとすれば、定期投資は「育てるお金」。
どちらも大切ですが、インフレが進む今の時代は、「守るだけ」ではジリ貧になる可能性が高いのです。
未来の安心をつくるには、今から少しずつ“育てる仕組み”を持つことが何よりの防衛策になります。
まとめ──“ほったらかし”は最強の資産形成戦略
2025年の資産形成におけるキーワードは、「自動化×長期×分散」。
人間の感情に左右されない「定期投資」は、まさにその条件をすべて満たす方法です。
●毎月自動で積み立てる
●時間を分散して購入
●10年以上、長期で育てる
この3つを続けるだけで、誰でも自然と「お金が増える体質」になれます。
定期預金のように安全で、投資のように賢い──そんな“ハイブリッドな貯め方”が、いまの時代の正解です。
「どんな投資信託を選べばいいか分からない」「自分に合うリスクの取り方を知りたい」──そんな方は、やさしい保険のFPにお気軽にご相談ください。
あなたのライフプランに合わせて、“ほったらかしでも安心できる”投資設計を一緒に考えます。
ご相談はこちら
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
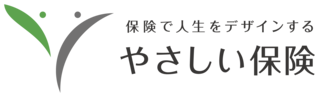

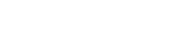

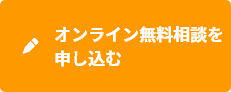
 VIEW MORE
VIEW MORE