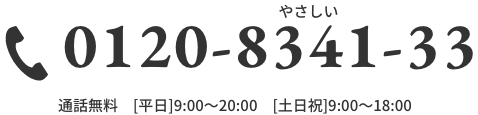住宅ローンと団信の誤解:保険を削ると老後が危険になる理由 2025-10-01 12:30:55

住宅ローンと団信の誤解:保険を削ると老後が危険になる理由
目次
はじめに
マイホームを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用します。その際に加入するのが「団体信用生命保険(以下、団信)」です。
金融機関からは「団信に入れば、万一のときローンがなくなるから安心ですよ」と説明されます。確かに、ローン返済中に契約者が亡くなった場合、残りの返済は免除され、家族に住まいを残せるのは大きなメリットです。
しかし、この「団信があるから生命保険は不要」と考えてしまうのは大きな落とし穴です。実際には、団信だけでは家族の生活を守りきれず、将来の老後資金にも深刻な影響を与えるケースが少なくありません。
本記事では、「団信=十分な保障」と思い込むことのリスクと、保険を削ることで老後が危険になる理由について解説していきます。
団信の基本的な仕組み
団信は、住宅ローンを借りる際に金融機関が加入を義務づける生命保険です。主な特徴は次の通りです。
●ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、残債が保険金で返済される
●保険金はあくまで「ローン残高」に充てられるもので、遺族が自由に使えるお金ではない
●三大疾病保障付きやがん保障付きの団信も増えているが、条件に該当しないと給付されない
つまり、団信は「住宅ローンを守るための保険」であり、「家族の生活を守るための保険」ではありません。
よくある誤解:「団信があるから保険は不要」
マイホームを購入した家庭でよくあるのが、「団信でローンは消えるから、生命保険を減らそう」「共働きだから必要ないのでは」という誤解です。
確かにローンは帳消しになりますが、次のような現実が待っています。
①生活費は保障されない
団信でローンがなくなっても、生活費や教育費は残ります。特に小さな子どもがいる家庭では、学費・塾代・進学費用などで数千万円単位の支出が必要です。
②老後資金が不足する
遺族年金は子どもが18歳になると打ち切られます。その後は配偶者の収入と貯蓄だけで生活を維持しなければなりません。結果的に老後資金の積み立てが滞り、「住宅は残ったが老後資金はない」という状況に陥りやすいのです。
③医療リスクには対応できない
団信は死亡または高度障害が条件です。がんや脳卒中で長期間働けなくなっても、団信は発動せず、収入減少とローン返済が重くのしかかります。
シミュレーションで考える
例えば、35歳夫・30歳妻・子ども2人の4人家族を想定します。住宅ローンは3,500万円、返済期間35年。団信には加入済み。
●夫が40歳で亡くなった場合:ローンは完済。しかし残された妻と子どもには生活費・教育費で約4,000万円以上が必要と試算されます。団信だけでは、全くカバーできません。
●夫が50歳でがんを患い、収入が途絶えた場合:団信は発動せず、住宅ローンの支払いは継続。結果的に妻の収入だけでは返済が難しく、家を手放すリスクもあります。
このように、団信に頼りすぎると「家は残っても生活が残らない」状態になるのです。
保険を削った結果、老後に何が起きるのか
住宅ローンを組んだタイミングで「支出を抑えたい」と考え、保険を削る家庭は多いです。しかし、その判断が老後に大きなツケを回します。
①教育費と生活費で貯蓄ができない
配偶者の収入と貯金だけでは、子どもの進学や生活維持で精一杯。老後資金の積み立ては後回しになります。
②退職金に依存するリスク
定年時にまとまった退職金が入っても、老後30年の生活を支えるには不十分。保険を削ったせいで貯蓄不足が解消できないケースが多発。
③介護リスクに対応できない
高齢期に介護が必要になると、毎月数万円~十数万円の費用がかかります。現役時代に備えをしていないと、老後の生活基盤が大きく崩れます。
ケーススタディ:二つの家庭の違い
Aさん夫婦(保険を削った家庭)
団信だけで安心と考え、生命保険をほぼ解約。夫が病気で働けなくなり、妻のパート収入と貯蓄で生活を維持。子どもの教育費に追われ、老後資金は貯まらず。60代に入り、家はあるが生活は厳しく、年金だけでは赤字に。
Bさん夫婦(必要保障を維持した家庭)
団信に加え、就業不能保険と死亡保障を確保。夫が働けなくなったが、保険金で生活費をカバー。教育費も計画的に積み立て、老後資金もiDeCo・NISAで準備。60代からは年金+積立資産で安定した暮らし。
両者の違いは「保険を削るかどうか」だけ。現役時代の判断が、老後30年の生活を大きく分けるのです。
保険を削る心理的な落とし穴
住宅ローンを組んだ直後は、「毎月の返済が始まるから、少しでも支出を減らしたい」という心理が働きます。その矛先が「生命保険の削減」になりやすいのです。
しかし、実際には 返済と同じくらい保障も重要な支出 です。ローン返済が順調でも、病気や死亡による収入減少で家計は一気に崩れます。「ローンさえ返せれば安心」と思うのは、団信に対する典型的な誤解です。
「保障を削る」のではなく「最適化」が正解
もちろん、過剰な保険に加入しているのは無駄です。しかし、団信を理由に極端に保険を減らしてしまうのは危険です。ポイントは「削る」ではなく「最適化」することです。
●死亡保障:子どもが独立するまでの期間は必要。団信と併用して、教育費や生活費をカバーできる額を確保。
●医療・就業不能保障:団信ではカバーできない長期療養や収入減少に備える。
●老後資金準備:保障とは別に、NISAやiDeCoで計画的に積み立てる。
これらを組み合わせることで、無駄を省きながらも「家族の生活と老後の安心」を守れるのです。
団信と保険をどう使い分けるべきか?
最後に、団信と生命保険の役割分担を整理します。
●団信:住宅ローンを守るための保険
●生命保険:家族の生活費や教育費を守るための保険
●医療・就業不能保険:働けなくなったときの収入を守るための保険
●資産形成(iDeCo・NISA):老後の生活を守るための仕組み
団信だけでは「家」しか守れません。人生全体を見据えるなら、団信を土台にしつつ、必要保障を上乗せするのが現実的です。
まとめ
「団信があるから保険は不要」という考え方は、住宅ローンを持つ家庭に広がる典型的な誤解です。団信が守るのはあくまで「住宅ローン」であり、家族の生活費や老後資金までは保障してくれません。
保険を安易に削ってしまうと、結果的に老後資金が不足し、住まいはあっても生活に困るという状況に陥りかねません。必要なのは「削減」ではなく「最適化」。団信を前提に、必要な保障と資産形成をバランスよく準備していくことが、家族の未来を守る最善の方法です。
ご相談はこちらから
「団信があるから保険は必要ないのでは?」と迷われている方は、一度ライフプランを一緒に確認してみませんか?
住宅ローンを組んだ今こそ、家族の生活と老後の安心を同時に守るための最適な保険設計が必要です。お気軽にご相談ください。
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
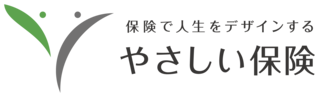

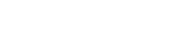

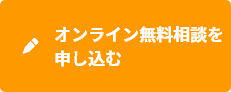
 VIEW MORE
VIEW MORE