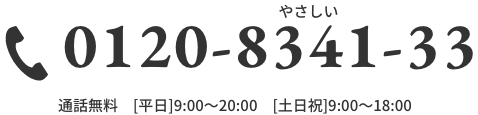75歳支給開始の現実味――「働けるうちに」備える老後戦略 2025-10-17 09:55:30

75歳支給開始の現実味――「働けるうちに」備える老後戦略
目次
はじめに:年金「75歳支給」の議論がついに現実味を帯びる
「年金の支給開始が75歳になるかもしれない」
これは決して“遠い未来の話”ではありません。日本の平均寿命は年々伸び、2025年には男性81歳、女性87歳を超えるといわれています。長生きが当たり前の時代になる一方で、年金制度は“支給年齢の引き上げ”という現実に直面しています。
もし支給が75歳からとなれば、60歳で定年を迎えてから15年間、収入の空白期間が生まれます。
この「15年」をどう過ごすかで、老後の安心度は大きく変わります。
「年金の支給開始が75歳になるかもしれない」
そんなニュースが報じられたとき、多くの人が「まさか」と感じたでしょう。
しかし現実は、すでにその方向へ静かに動き始めています。
現在の年金制度では、原則65歳から受け取ることができますが、繰り下げ受給を選べば75歳まで遅らせることも可能。
そして政府の財政検証では、「平均寿命の延び」や「現役世代の減少」を背景に、将来的な支給開始年齢の引き上げが検討されているのです。
つまり、「75歳支給」が“選択”ではなく“基準”になる日が、決して遠くないということ。
そのとき、あなたの生活設計はどう変わるでしょうか。
年金は「もらえる時期」ではなく「生きる期間」で考える時代
日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳(令和5年厚労省調査)。
一方、健康寿命はそれより約10年短いと言われます。
つまり、「元気に働ける期間」と「年金に頼る期間」は、年々長くなっているのです。
もし支給開始が75歳に引き上げられたら?
65歳で定年を迎えてからの10年間は、自分の力で生活費を賄わなければなりません。
この“空白の10年”をどう乗り切るかが、今後の老後戦略のカギとなります。
「75歳支給」のインパクト:10年間で約2,000万円の差に?
仮に、現在の支給額(月15万円)を基準に考えましょう。
65歳から受け取れば年間180万円、10年で1,800万円。
つまり、支給が75歳まで遅れれば、この期間に約2,000万円近い収入ギャップが生まれます。
貯金で補うには厳しく、年金だけに頼る生活はもはや現実的ではありません。
「働けるうちに備える」という意識が、これからの常識になります。
老後資金の3本柱:「公的年金」「私的年金」「運用」
では、どのように準備すればよいのでしょうか。
FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から見ると、老後の安定収入を作るには3つの柱が必要です。
1️⃣ 公的年金(国民年金・厚生年金)
→ 国の最低限の保障。制度の変更に左右されやすい。
2️⃣ 私的年金(企業年金・iDeCo・個人年金保険など)
→ 税制優遇を活かせば効率的な積立が可能。
3️⃣ 資産運用(投資信託・NISAなど)
→ インフレに強く、長期的に資産を増やせる。
この3本をバランスよく組み合わせることが、75歳支給時代を生き抜く「現実的な老後戦略」となります。
“働けるうちに”がキーワードになる理由
老後の備えは、「老後になってから」では遅い。
特に30代・40代は、時間を味方にできる最後のチャンスです。
複利の効果は、早く始めるほど大きくなります。
たとえば毎月3万円を年利3%で運用した場合、
30歳から65歳まで35年間続けると、元本1,260万円が約2,100万円に。
45歳から始めると、同じ条件でも約980万円しか増えません。
つまり、“今始める”か“10年後に始める”かで、1,000万円以上の差が生まれるのです。
「退職後も働く」は前提に。70歳以降の働き方改革
政府もすでに「70歳までの就業機会確保」を企業に努力義務化。
今後は“定年後も働く”ことが当たり前の社会になります。
ただし、体力やスキルの差によって、収入格差が広がるのも事実。
75歳支給時代に備えるなら、**「何歳まで・どんな形で働けるか」**を意識したライフプランが重要です。
おすすめは、
●副業・フリーランススキルの習得
●在宅でできる仕事の確保
●健康維持への投資(運動・食生活・メンタルケア)
「健康」「スキル」「資産」——この3つがそろって初めて、“選べる老後”が手に入ります。
老後の生活費を減らす“固定費見直し”も戦略の一つ
資産形成と並行して、支出を減らすことも重要な備えです。
特に、以下の3つの見直しは効果が大きいです。
●保険の最適化:保障が重複していないかを確認
●スマホ・サブスク料金の見直し:毎月数千円でも積み重ねれば大きな差
●住宅ローンの借り換え・繰上げ返済:退職前に完済できる仕組みづくり
“節約”ではなく“設計変更”として考えることで、生活水準を落とさずに老後資金を増やせます。
「老後不安」を“行動”に変える
多くの人が老後に不安を感じていても、行動に移せないのはなぜでしょうか。
答えはシンプルで、「何から始めればいいかわからない」から。
そんな時こそ、専門家を味方につけるのが近道です。
保険・iDeCo・NISA——それぞれの特徴を整理し、自分の将来像に合わせて戦略を立てる。
これが、“老後不安を見える化”する第一歩になります。
公的年金は「支え合い」から「自己防衛」へ
年金制度の仕組みは“現役世代が高齢者を支える”構造です。
しかし、少子高齢化によってそのバランスは崩れつつあります。
1960年には現役11人で1人の高齢者を支えていましたが、現在は2人で1人。
2040年には1.3人で1人を支えるとも言われています。
つまり、将来的には「もらう額」よりも「負担する額」が上回る構造が続く可能性が高いのです。
国もこの現実を踏まえ、「働けるうちは働く」「自助努力で資産形成する」方向に制度設計を進めています。
老後に必要な金額は「2,000万円」ではない
「老後2,000万円問題」という言葉が話題になりましたが、実際には人によって必要金額は大きく異なります。
たとえば、
- 住宅ローンが残っている
- 子どもの教育費がまだ必要
- 親の介護費用を支援している
といったケースでは、2,000万円では全く足りません。
また、75歳支給開始が現実になれば、10年間で約1,800万円の収入ギャップが発生すると言われています。
月15万円×12カ月×10年=1,800万円。
つまり、「定年後の10年分の生活費」をどう賄うかが課題です。
“資産寿命”を延ばすという考え方
金融庁が提唱しているのが、「資産寿命を延ばす」という発想。
単に“貯める”だけでなく、運用しながら取り崩す仕組みを作ることが大切です。
たとえば、
●公的年金:毎月の生活費のベース
●運用資産(NISA・iDeCo):不足分を補う
●保険年金:長生きリスクに備える
このように“3段階で収入を組み合わせる”ことで、長生きしても安心なキャッシュフローが完成します。
「健康だから大丈夫」では通用しない時代に
多くの人が「健康で働けるうちは大丈夫」と思いがちですが、実はその油断が一番危険です。
がんや脳卒中、心疾患など、突然の病気で働けなくなるリスクは誰にでもあります。
就業不能になったとき、収入が途絶えれば、年金までの“空白期間”を乗り切ることは困難です。
その意味で、医療保険や就業不能保険の加入は「老後対策の一部」として考えるべきです。
老後のための資産形成と、働けなくなったときの保障はセットで準備するのが今の常識になりつつあります。
まとめ:「働けるうちに」があなたの最大の資産
75歳支給が現実になっても、「働けるうちに準備していた人」と「何もしてこなかった人」では、老後の安心感がまるで違います。
老後は“年金でもらう時代”から、“自分でつくる時代”へ。
年金制度を嘆くより、自分の力で未来をデザインする方が、ずっと現実的です。
健康で働ける今こそ、資産づくりのスタートライン。
「老後を不安に思う時間」を、「老後を準備する時間」に変えていきましょう。
老後資金の備え、今から始めませんか?
やさしい保険では、iDeCo・NISA・保険のバランス設計を含めた「老後資金相談」を無料で実施しています。
「いくら準備すれば安心か」「どんな保険が老後に強いのか」──
気になる方は、まずはお気軽にご相談ください。
将来の安心は、“今日の一歩”から始まります。
「自分に必要な老後資金は?」「どんな保険を組み合わせれば安心?」——
FPがあなたの未来設計を一緒に考えます。
→ [無料相談はこちら]
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
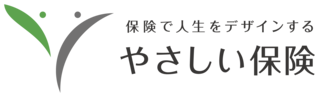

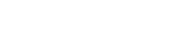

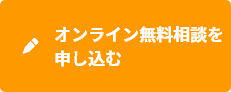
 VIEW MORE
VIEW MORE