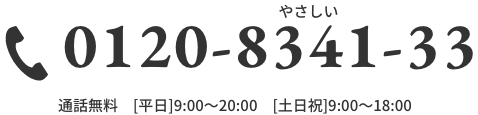「年金は75歳から」は本当?──データで読み解く将来の受給戦略 2025-10-03 10:59:54

「年金は75歳から」は本当?──データで読み解く将来の受給戦略
目次
はじめに
「年金は75歳から受け取るようになる」「年金支給開始年齢が引き上げられるらしい」——そんな話を耳にしたことはありますか?結論から言うと、公的年金の「支給開始年齢が一斉に75歳に変更される」わけではありません。しかし制度の柔軟化や高齢就労の拡大を受けて、受給の選択肢として「最大75歳まで繰り下げて受け取ることが法的に認められている」点は事実です。公的な法改正で繰下げの上限が75歳に拡大されたこと、そして高齢者の就労率や財政検証の議論が続いていることを踏まえ、将来の受給戦略をどう立てるかをデータと制度面で整理します。厚生労働省+1
まずは事実確認:「75歳」が意味するもの
重要なのは「75歳」という数字の意味です。現在(制度上)は原則65歳が年金の標準的な受給開始年齢ですが、受給開始を繰り下げることで年金額を増やす制度(繰下げ受給)があり、法改正によりその繰下げ上限が「75歳」まで拡大されています。つまり「75歳から受け取らなければならない」わけでも、「65歳受給が消える」わけでもありません。受給開始の選択肢の上限が拡がった、という点が正確な理解です。厚生労働省
繰下げの効果は分かりやすく、1か月ごとに0.7%増額(最大で75歳までなら+84%)となります。仮に65歳受給をやめて75歳まで待てば年金支給額は大幅に増えますが、その間は年金が支払われないため生活資金を別に確保する必要があります。MUFG銀行
データが示す高齢期の働き方と年金の関係
近年、日本では65歳以上の就労が増え、「老後も働く」ことが一般的になりつつあります。研究・統計を見ると、60〜74歳の就業率は世代や性別で差はあるものの高齢者の就業は確実に拡大しています。高齢期に働くことで、受給開始を遅らせながら就労収入で生活を賄う選択肢が現実的になってきました。これが「繰下げ受給の現実的需要」を後押ししています。日本の法令検索
ただし、働きながら年金を受けると在職老齢年金による支給調整(支給停止等)が発生する場合があるため、繰下げメリットの実効性は働き方(厚生年金加入かどうか、収入額)に左右されます。年金を増やす目的で繰下げるなら、在職状況と支給調整のルールを必ず確認する必要があります。社会保険.jp
「75歳受給」のメリット・デメリット(数字で考える)
メリット
●長く繰り下げるほど年金が大きく増える(最大+84%)。長生きリスクに備えた収入増加策として有効。MUFG銀行
●他の資産(貯蓄や運用資産)を年金支給前に取り崩して使い、年金開始後は増えた年金を長期間受け取る戦略が取りやすい。
デメリット
●繰下げ期間中は年金がゼロのため、代替の収入源や十分な貯蓄がないと生活が苦しくなる。
●短命リスク(早期に死亡した場合)は、繰下げた分の年金を受け取れない損失につながる。平均寿命と健康状態の見立てが重要。
●在職による支給減額や税・社会保険料負担の変化により、繰下げ効果が目減りする場合がある。社会保険.jp
ここからわかるのは「繰下げは万能ではない」という点です。年金を増やす”槓杆”としては強力ですが、個人の寿命見通し、貯蓄、就労計画、税や保険料の影響を総合的に判断する必要があります。
具体的な受給シミュレーションの考え方
①標準受給(65歳):早期死亡リスクを回避し、確実に年金収入を確保したい人向け。老齢基礎年金・老齢厚生年金を早期から受け取るため、資金的安全性が高い。
②部分繰下げ(66〜69歳など):年金を少し増やしつつ、繰下げ期間を短くしてリスクとリターンをバランス。就労を続けつつ取り得る現実的な選択。
③最大繰下げ(〜75歳):年金を大きく増やし長生きリスクに備える戦略。退職後も一定の就労収入や貯蓄で生活でき、長期的に年金に依存したい人向け。
数値目安:たとえば65歳からの年金を受ける代わりに75歳まで待てば年金額は約1.84倍になる(法定上の最大増額)。ただし、この「約1.84倍」が家計にプラスになり続けるかは、繰下げ期間中の払出し資金、税金、保険料、健康寿命に強く依存します。MUFG銀行
若い世代(30〜50代)にとっての現実的戦略
若いうちに考えるべきポイントは以下の通りです。
①繰下げを“基本に置かない”
繰下げは選択肢として有用だが、若いうちは「繰下げ前提で資産形成を放置する」リスクがある。まずは基礎的な老後資金(生活防衛資金)と投資・iDeCo・NISAなどの長期運用を確保することが優先。年金機構
②働き方の設計
定年・再雇用・副業など、自分がどの程度まで就労を続けられそうかを見積もる。働く意欲と健康が見込めるなら繰下げも現実味を帯びる。JILなどのデータは高齢者の就業が可能であることを示しているが、個人差は大きい。日本の法令検索
③税・社会保険の影響を見積もる
年金受給額が増えれば所得税や医療・介護保険料の扱いが変わる。繰下げによる増加が手取りベースでどの程度影響するかを試算すること。年金機構
実務的チェックリスト(受給決断前に必ず確認)
●自分の想定平均寿命や健康状態の見通しはどうか。
●繰下げ期間(例:65→70→75)に必要な生活資金は確保できるか。
●就労収入を当てにする場合、在職老齢年金の調整や厚生年金加入の有無を確認したか。社会保険.jp
●年金増額後の税金・社会保険料の変化を把握したか。年金機構
●家族構成(配偶者の年金、健康状態、相続・遺族年金)を含めた家庭全体の収支を試算したか。
これらは年金受給開始を決めるうえで不可欠な視点です。単に「受給を遅らせれば得」ではなく、「誰が、いつ、どのくらい受け取れるか」を家計全体で見ることが重要です。
結論:75歳から受給が“義務化”されるわけではないが、選択肢は広がった
まとめると、次の点が肝です。
●「年金は一斉に75歳から」は誤り。受給開始年齢の標準は変わらないが、繰下げの上限が75歳に拡大されたことで「最大で75歳まで待てる」ようになったのは制度上の事実。厚生労働省+1
●繰下げは長生きリスクに備えられる強力な手段だが、繰下げ期間中の生活資金、在職による調整、税負担、健康リスクなど複数要因でメリットが左右される。社会保険.jp+1
●若い世代はまず「老後の基礎を外部に依存しすぎない形で作る」こと(貯蓄・投資・iDeCo・NISA等)を優先し、そのうえで繰下げも含めた長期戦略を練るのが現実的。年金機構+1
主な参考・出典
●厚生労働省:年金制度改正(繰下げ上限75歳等)に関する情報。厚生労働省
●日本年金機構:年金額等に関する最新情報(年金額の例等)。年金機構
●金融機関や解説記事:繰下げ増額率等の解説。MUFG銀行
●労働政策・研究機関(JIL)等:高齢者の就業動向等のデータ。日本の法令検索
海外制度との比較から見える日本の特徴
日本の年金制度は「65歳支給開始が原則、繰下げは75歳まで可能」という仕組みですが、海外に目を向けると「年金開始年齢の柔軟化」は先進国で共通の流れです。たとえば米国の社会保障年金(Social Security)は「62歳から早期受給」もできる一方、「70歳まで繰り下げる」と増額される制度です。イギリスでも国家年金は受給開始年齢を段階的に引き上げ、繰下げによる増額が用意されています。つまり「75歳」という数字自体は日本特有ですが、「長寿化に合わせて受給開始を遅らせるインセンティブを設ける」という方向性は国際的な潮流だといえます。
この背景にあるのは、どの国も「財政負担の増大」と「長寿リスク」への対応です。寿命が伸び続けるなかで「同じ年齢で一律に年金を支給すると制度が持たない」という共通課題があり、日本も例外ではありません。
財政検証が示す将来のシナリオ
厚生労働省は5年ごとに「年金財政検証」を行い、将来の制度持続性を試算しています。直近の検証では、経済成長が順調に進めば現行制度を維持可能とされていますが、低成長シナリオでは「所得代替率(現役世代の収入に対する年金額の割合)」が50%を下回るリスクも示されています。これはつまり、「65歳から年金をもらっても、生活を維持するのが難しい層が増える」可能性を意味します。その場合、繰下げによって年金を増やす選択が現実的に必要になる人が増えるでしょう。
一方で「繰下げをしたくても、生活資金が足りず待てない人」が出ることも予想されます。ここが「資産形成や私的年金の準備を早めに始めるべき理由」です。国の制度に頼るだけではなく、自分のライフプランに応じた備えが必要になるのです。
実際に繰下げを選んだ人の声(事例イメージ)
事例A:70歳まで働き、繰下げを選択した男性(元公務員)
65歳時点で退職金と貯蓄が十分にあり、70歳まで嘱託勤務を続けた。生活費は給与で賄えたため年金を繰下げ、結果的に月額年金は約1.4倍に。健康寿命が長く、現在80歳を超えても年金を十分に享受できている。
事例B:繰下げを断念した女性(自営業)
65歳以降も働くつもりだったが、体調を崩し、収入が途絶えたため繰下げは困難に。結局65歳から受給開始に切り替えた。「元気なうちは繰下げを考えられたが、健康リスクは読めない」と振り返っている。
このように「繰下げ戦略の成否」は健康・収入・貯蓄の3要素に強く左右されます。だからこそ繰下げは「選べる人だけが得をする制度」ともいえるのです。
まとめ
「年金は75歳から」というフレーズは誤解を招きますが、制度が柔軟化して選択肢が広がったのは事実です。海外でも同様に「長寿化に合わせて年金受給を後ろ倒しする流れ」が進んでいます。将来の財政見通しを踏まえると、繰下げは一部の人にとって魅力的な戦略ですが、誰にでも有利とは限りません。
健康状態や就労状況を正直に見極め、ライフプランと照らし合わせながら選択することが、これからの老後戦略のカギになります。
最後に
年金は制度自体が複雑で、個別事情で有利・不利が大きく変わります。具体的な受給シミュレーション(想定寿命、貯蓄、就労計画、税負担、配偶者の年金などを組み込む)を行い、65・66・70・75歳受給それぞれの生涯手取りを比較することを強くお勧めします。公的機関や市町村の年金相談、ファイナンシャルプランナーへの相談で数パターンを試算してみてください。年金機構
やさしい保険でも、あなたのライフプランに合った「年金受給の最適解」を一緒にシミュレーションできます。まずは現状の年金見込み額・貯蓄・就労見通しを整理することから始めましょう。ご希望があれば、簡易試算のテンプレート(入力項目リスト)をこちらで作成します。ご利用になりたいですか?
老後資金や年金戦略は、一人ひとりの働き方・家族構成・ライフスタイルによって大きく変わります。ニュースやネットの情報だけでは、自分に最適な答えを導くのは難しいものです。
「私の場合はどうしたらいい?」と感じられた方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。やさしい保険では、将来の年金受給を見据えた資産形成や保険の見直しについて、分かりやすく丁寧にアドバイスを行っています。
下記のお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
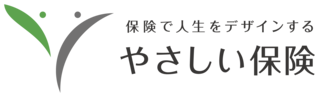

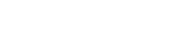

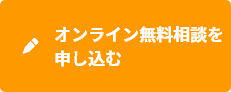
 VIEW MORE
VIEW MORE