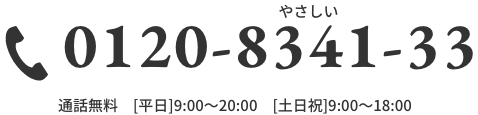健康でも危険信号!生活費6カ月分の貯金がない人の盲点 2025-09-04 12:59:32

健康でも危険信号!生活費6カ月分の貯金がない人の盲点
目次
はじめに
「自分は健康だから大丈夫」「貯金が少なくても毎月の収入があるから困らない」──そう考える方は少なくありません。しかし、実際には健康であっても、突然の病気やケガによって“働けない期間”が訪れる可能性があります。とくに生活費6カ月分の貯金がない場合、日常生活を支える力が一気に脆弱になるのです。本記事では、働けなくなったときに直面する現実と、公的保障の限界、そして具体的な備えについて解説します。
健康=安心ではない現実
「病気にならない限り収入は途切れない」と考えてしまいがちですが、現実は異なります。がんや心筋梗塞、うつ病など長期療養が必要な病気は、若い世代でも発症する可能性が十分あります。厚生労働省の統計によれば、がんの罹患率は40代から急増。さらに、うつ病や適応障害による休職者は20代・30代にも広がっています。
つまり、健康な今がずっと続く保証はなく、突然「働けない」状態に陥るリスクは誰にでもあるのです。
生活費6カ月分の貯金がない人が直面する盲点
多くの家庭で「生活費の予備資金は1〜2カ月分程度」しかありません。家賃や住宅ローン、食費、水道光熱費、教育費…収入が止まっても支出は止まりません。仮に毎月25万円の生活費が必要なら、6カ月で150万円が必要です。
しかし、総務省の調査では、日本人の平均貯蓄額は高い一方で「中央値」はわずか数百万円台。つまり半数以上の世帯は、半年間の生活費を確保できていないのです。
公的保障の限界
会社員であれば「傷病手当金」がありますが、支給額は給与の約3分の2。さらに最長1年半で打ち切られます。フリーランスや自営業にはこの制度すらありません。
一方で、生活保護は資産や扶養義務の有無が厳しくチェックされ、誰もが利用できるわけではありません。「公的保障があるから安心」と思っていると、実際に働けなくなったときに生活が維持できない現実に直面します。
ケーススタディ:突然のがんで収入ゼロに
Aさん(35歳・会社員・既婚・子ども2人)は健康そのものでした。しかし、突然のがん診断で半年以上の休職に。傷病手当金は支給されたものの、手取りは以前の3分の2に減少。住宅ローンや教育費が重なり、生活は一気に赤字に。貯金は3カ月で底をつき、親に借金を頼らざるを得ませんでした。
もし生活費6カ月分の貯蓄か、就業不能保険があれば、生活破綻を防げたケースです。
実際に必要な備えの目安
「生活費6カ月分」といっても実際の金額は人によって異なります。例えば独身で実家暮らしなら月15万円で済むかもしれませんが、住宅ローンと子どもの教育費がある家庭なら月40万円以上が必要です。
必要額を把握するために、まずは1カ月の固定支出を洗い出すことが重要です。その上で、「最低でも3カ月、理想は6カ月分」の生活費を現金または保険でカバーする仕組みを作りましょう。
さらに、現金だけで備えるのは現実的に難しい場合もあります。そこで役立つのが「就業不能保険」や「収入保障保険」です。これらは働けなくなったときに毎月の生活費を補填するため、貯金が少なくても安心を得られます。
①活費6カ月分の貯金が目安とされる理由
金融機関や家計管理の専門家が「生活費6カ月分の貯金」を推奨するのには根拠があります。
1〜2カ月の休業であれば有給休暇や短期の傷病手当金で何とか凌げます。しかし、治療や療養が長引けば、3カ月・6カ月と収入が途絶えることも珍しくありません。特に自営業やフリーランスの場合、公的保障がほとんど受けられず、即座に家計が圧迫されます。
また、住宅ローンや教育費など固定的な支出は待ってくれません。収入がゼロになっても、毎月出ていく支払いは続くため、6カ月分の生活費を貯蓄として確保しておくことが「最低限の備え」とされているのです。
②「健康だから大丈夫」が落とし穴になる
多くの人は「病気になるのは高齢になってから」と思いがちですが、就業不能のリスクは若年層にも訪れます。
●うつ病などのメンタル疾患
●がんの発症
●交通事故による長期入院やリハビリ
これらは30代・40代でも発症・発生率が高く、実際に職場復帰まで半年以上かかるケースも少なくありません。健康に自信があっても、「ある日突然」働けなくなる現実があるのです。
③公的保障だけでは足りない現実
会社員であれば「傷病手当金」がありますが、標準報酬月額の約3分の2しか受け取れません。さらに支給は最長1年6カ月まで。フリーランスや自営業の場合は、この制度すら利用できません。
一方、医療保険は入院や手術にかかる医療費をカバーしますが、家賃や住宅ローン、食費、教育費などの「生活費」までは補えません。つまり、公的保障と医療保険の両方があっても、収入減による生活の維持までは守りきれないのです。
④就業不能保険という選択肢
ここで注目すべきなのが「就業不能保険」です。これは病気やケガで長期間働けなくなった場合に、毎月の生活費を補填するための保険です。
●働けない間、毎月一定額の給付金を受け取れる
●長期的な療養やメンタル疾患にも対応する商品がある
●住宅ローン返済をカバーするための専用プランも存在
就業不能保険を活用すれば、「収入ゼロ」という最悪のシナリオを防ぎ、貯金の取り崩しを最小限に抑えることができます。
⑤ケーススタディ:もしあなたが働けなくなったら
仮に月収30万円の会社員がうつ病で1年間休職した場合を想定してみましょう。
●傷病手当金:約20万円×12カ月=240万円
●実際の生活費:30万円×12カ月=360万円
→ 1年間で約120万円の赤字
これを貯蓄で補おうとしても、生活費6カ月分(180万円)の貯金しかなければ、1年持たずに底をつきます。
一方、就業不能保険で毎月10万円が給付されれば、赤字はほぼ解消され、貯金を守りながら生活を維持できるのです。
⑥「貯金で備える」と「保険で備える」の違い
もちろん、十分な貯金があれば安心ですが、現実には生活費6カ月分すら貯められていない世帯が多数派です。貯金だけで備えるには時間も労力もかかり、途中で予期せぬ出費により取り崩すリスクもあります。
保険で備える場合、少額の保険料で「長期の生活費」をカバーできるため、効率よくリスクを分散できます。貯金と保険、両方をバランスよく組み合わせることが現実的な解決策なのです。
⑦専門家に相談するメリット
就業不能保険にはさまざまな種類があり、条件や給付内容は保険会社によって異なります。自分に合った保障額や期間を判断するのは簡単ではありません。そこで、保険のプロに相談することで、
●家計に合った保険料で必要な保障を確保できる
●公的保障や既存の保険とのバランスを最適化できる
●無駄な重複保障を避け、コストを抑えられる
といったメリットを得られます。
まとめ:今こそ“働けないリスク”に備える時
「健康だから大丈夫」と思っている今こそ、就業不能リスクへの備えを考えるタイミングです。生活費6カ月分の貯金がない人にとっては、なおさら早急な対策が必要です。
就業不能保険は、医療保険や死亡保険とは異なり、“働けないけれど生きている”という現実をカバーしてくれる数少ない制度です。家族の生活を守るために、ぜひ一度ご自身の保障内容を確認してみてください。
「うちは貯金が少ないけど大丈夫?」「どの保険が自分に合うのかわからない」──そんな不安を感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門のファイナンシャルプランナーが、あなたの家計とライフプランに合わせて、最適な備え方を一緒に考えます。
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
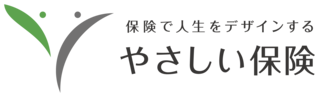

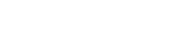

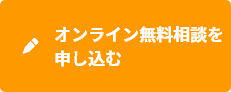
 VIEW MORE
VIEW MORE