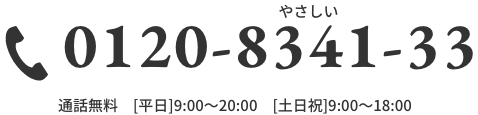「働けないリスク」にどう備える?生命保険でカバーできる就業不能の現実 2025-09-02 10:03:41

「働けないリスク」にどう備える?生命保険でカバーできる就業不能の現実
目次
はじめに
私たちの生活は、毎月の給与によって成り立っています。住宅ローンの返済、子どもの教育費、日々の生活費──これらの多くは「働いて収入を得ること」が前提です。
しかし、もし病気やケガで長期間働けなくなったらどうなるでしょうか?
「自分は健康だから大丈夫」「入院しても医療保険があるから安心」──そう考えている方も少なくありません。
ところが実際には、就業不能状態が家計に与えるインパクトは、想像以上に大きいのです。今回は、生命保険でカバーできる「就業不能保障」にスポットを当て、その必要性と活用方法を解説していきます。
就業不能とは?医療保険や傷病手当金では足りない現実
一般的に「就業不能」とは、病気やケガにより一定期間以上、仕事を続けられない状態を指します。
会社員であれば、健康保険から「傷病手当金」が支給される仕組みがあります。給与の約3分の2が最長1年半支給されるため、一見すると安心に思えるかもしれません。
しかし、次のような課題があります。
●支給額は手取りよりも少ない(社会保険料や住民税の支払いは続く)
●自営業者やフリーランスには制度がない
●最長1年半で終了するため、長期療養には対応できない
また、医療保険は「入院や手術の費用」をカバーする商品であり、生活費の補填には直結しません。
つまり「医療費は払えるけれど、生活費が足りない」というギャップが生まれるのです。
働けなくなるリスクは誰にでもある
厚生労働省の統計によると、働き盛りの30代・40代でも長期療養が必要になるケースは少なくありません。
●がんの罹患率は40代から急増
●精神疾患による休職は20代後半〜30代に多い
●脳卒中や心疾患は突然発症し、長期リハビリが必要になることも
「高齢になってからの病気」だけがリスクではなく、むしろ住宅ローンや子育てで支出が大きい時期に発症することで、家計が一気に破綻する危険性があります。
家計シミュレーション:働けなくなったら生活はどうなる?
ここで、実際にシミュレーションしてみましょう。
ケース①:30代会社員、手取り月30万円
●住宅ローン:10万円
●教育費:3万円
●生活費:12万円
●その他(保険料・通信費など):5万円
通常なら収支はトントン。しかし、病気で休職し傷病手当金が月20万円になった場合──
●住宅ローンや生活費は変わらず必要
●毎月の収支はマイナス10万円
●貯蓄が300万円あっても、2年半で底をつく
ケース②:40代フリーランス、独身、手取り月25万円
●家賃:7万円
●生活費:12万円
●その他:6万円
働けなくなったら収入はゼロ。貯蓄がなければすぐに家賃が払えなくなり、生活基盤が崩壊するリスク大。
このように、就業不能は「入院費よりも怖い家計の赤字」を生みます。
生命保険の就業不能保障とは?
こうしたリスクに対応するのが、生命保険会社が販売する「就業不能保険」や「就業不能保障特約」です。
一般的な仕組みは以下の通りです。
●病気やケガで所定の就業不能状態になった場合、毎月一定額の給付金を受け取れる
●支給期間は「最長2年」「60歳まで」「一生涯」など商品によって異なる
●医師の診断や入院日数ではなく、働けるかどうかで判断される
つまり、生活費を直接サポートする仕組みであり、医療保険の空白部分を埋める存在と言えます。
他の保障との違い
よく混同されるのが「収入保障保険」や「障害年金」です。
●収入保障保険:死亡時に毎月給付金を受け取れる。
●障害年金:国の制度。障害等級が重度でないと受け取れない。金額も月数万円と生活費を賄うには不足。
●就業不能保障:死亡ではなく「働けない状態」に備える。日常生活に必要な資金を補填できる。
それぞれの役割が異なるため、就業不能リスクを直接カバーできるのは就業不能保障だけなのです。
就業不能保障が必要な人・不要な人
では、誰にでも必要なのでしょうか?実際にはライフスタイルや貯蓄状況によって変わります。
必要性が高い人
●住宅ローンなど大きな固定費を抱えている
●子どもが小さく教育費がこれからかかる
●貯蓄が十分でない(半年〜1年分の生活費に満たない)
●自営業やフリーランスで公的保障が薄い
必要性が低い人
●既に十分な資産や不労所得がある
●配偶者の収入で生活を維持できる
●独身で生活費が少なく、家族の扶養義務がない
自分に必要か?チェックリスト
- ✅ 住宅ローンの残高が1,000万円以上ある
- ✅ 教育費のピークはこれから
- ✅ 貯蓄は生活費6カ月分未満
- ✅ 自分が収入を失うと家計が赤字になる
- ✅ 自営業・フリーランスで傷病手当金がない
2つ以上当てはまる人は、就業不能保障を検討する価値が高いでしょう。
保険料はどれくらい?
就業不能保障の保険料は、年齢・性別・保障額・支払期間によって変わります。
例として、30代男性が「月額15万円の給付金、60歳まで支給」の契約をすると、保険料は月3,000〜5,000円前後が目安です。
「毎月のランチ代程度で、もしもの生活費を確保できる」と考えると、コストパフォーマンスは決して悪くありません。
実際の事例
事例①:30代男性・会社員
営業職のAさん(35歳・既婚、子ども2人)は、くも膜下出血で倒れ、半年間の入院とリハビリが必要になりました。
傷病手当金は支給されたものの、住宅ローンと教育費の負担で家計は赤字に。就業不能保険を契約していたことで、毎月15万円が給付され、生活を維持することができました。
事例②:40代女性・フリーランス
デザイナーのBさん(42歳・独身)は、うつ病で長期間仕事ができなくなりました。公的な傷病手当金はなく、医療保険の入院給付金も短期間で終了。
就業不能保険を契約していなかったため、生活費は貯蓄を取り崩すしかなく、結果的に老後資金が大幅に減ってしまいました。
このように、加入の有無で生活の安定度が大きく変わります。
就業不能保険の選び方
①給付額を生活費ベースで計算
→ 住宅ローン、教育費、生活費から「最低限必要な金額」を割り出す。
②給付期間を確認
→ 一時的な保障で十分か、60歳までの長期保障が必要かを判断。
③免責期間を把握
→ 契約によって「60日後から給付開始」など条件が異なる。
④医療保険や死亡保障とのバランス
→ 全体の保険料負担を見ながら調整する。
まとめ:働けないリスクは保険でしか守れない
就業不能のリスクは、誰にとっても「明日の自分」に起こり得る現実です。医療保険や貯蓄だけではカバーしきれない部分を補い、家族の生活を守るためには、生命保険の就業不能保障が大きな役割を果たします。
「まだ若いから大丈夫」と思っているうちに準備することが、最も賢いリスク管理です。
👉 [無料相談はこちらから]
やさしい保険では、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた就業不能保障のご提案を行っています。
「うちの家計に本当に必要なのか知りたい」「いくらくらいの保障額が適切か相談したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
-
家計も、保険も、資産運用も!
大事なお金のこと、
どなたでもお気軽にご相談ください。 -
やさしい保険は、税金・年金・保険・ライフプランなど
大事なお金のことを「お金のプロ」に
無料でご相談いただけるサービスです。
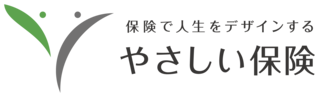

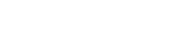

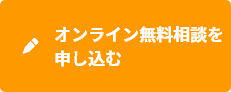
 VIEW MORE
VIEW MORE